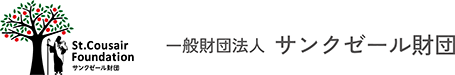地域で育む、子どもたちの未来(中高生・若者ほっとキッチン・無料学習塾)
こんにちは、サンクゼール財団です。
サンクゼール財団では、活動の第一歩として子ども食堂団体への訪問を行っています。
“子ども食堂”と一言で言っても、その活動内容は団体によりさまざま。運営状況やお困りごとなどをヒアリングし、現場の意見を大切にした助成事業を立ち上げるべく、長野県内の子ども食堂へお伺いし調査を行っています。
2025年3月に、長野県長野市の子ども食堂「中高生・若者ほっとキッチン・無料学習塾」様(以下、ほっとキッチン)へ訪問させていただきました。一人ひとりの事情や気持ちに寄りそった支援を行う、ほっとキッチンの活動の様子をレポートします。
中高生・若者ほっとキッチン・無料学習塾 概要
会場:長野市中部公民館第五地区分館
開催日時・活動内容:
第一土曜日 10時~12時 絵画教室「絵遊び」・学習支援
第二土曜日 10時~13時 学習支援、若者の居場所(ゲーム、将棋、ギター等)、会場での食事提供、食材・弁当配布
第三土曜日 10時~12時 学習支援
第四土曜日 10時~13時 学習支援、若者の居場所(ゲーム、将棋、ギター等)、会場での食事提供、食材・弁当配布
参加費:無料
”おいしい”の裏にある、たくさんの手間
ボランティアの皆さんは、朝から食事の準備に取りかかります。
この日は、会場での食事提供に加えて、配布用のお弁当作りや食品詰め合わせセットの準備もあり、大忙し!
地区の公民館を借りての活動なので、ほっとキッチンの備品を会場に常設しておくことができません。そのため毎回の準備や後片付けも一苦労です。


食品詰め合わせセットは、お渡しする先の家族構成に合わせて量を調整しています。
フードバンクなどから受け取った食品を、組み合わせや量を調整してセットします。

希望を支える学びの時間
別室では、無料の学習塾が開かれていました。
この日は、生徒1名に対して先生が2名という体制。英語と数学のワンツーマン指導が行われていました。分からないことは、じっくり質問できます。
そして、嬉しいニュースもお聞きしました。
この春、ほっとキッチンで学んでいた中学生2名が、それぞれ志望校に合格したそうです。どちらも地域で知られる進学校!!
無料学習塾を始めて5年目を迎える中で、こうした成果が着実に現れていることに驚きました。
ボランティアの皆さんによる指導やサポートの力はもちろんですが、何よりも子どもたち自身が学ぶ意欲を持ち、努力を重ねた結果ですね。

食事を通してつながる、子どもと地域の絆
「ご飯の準備ができたよ」という声がかかると、和室にみんなが集合し、食卓を囲みます。
顔なじみのメンバーが多く、和やかであたたかい雰囲気が広がっていました。
この日は、中学校と高校をそれぞれ卒業する子どもたちをお祝いする場面もありました。
「ここのおかげです」「社会人になっても頑張ります」といった素直な感謝の言葉に、思わず胸が熱くなります。
ボランティアの皆さんも、自分のことのように嬉しそうな表情を浮かべていました。
「ここに来る子どもたちは、私たちボランティアのおばちゃんにとっては孫のような存在なんです」
そう語ってくださったのは、ほっとキッチンの代表を務める小林さん。
“孫”という言葉に、思わず納得してしまいました。
ほっとキッチンのあたたかい雰囲気は、まるでおばあちゃんの家に遊びに来たときのような、そんな懐かしさと安心感を感じさせてくれます。

来てもいいし、来なくてもいい。
勉強してもいいし、遊んで過ごしてもいい。
一人ひとりの「やりたいこと」や「できること」を、そっと尊重してくれる――そんな空気が、言葉が無くても伝わってきます。
運営者へのインタビュー
食事をいただいた後、ほっとキッチンの代表を務める小林さん、スタッフの中山さん、高戸さんにお話をお聞きしました。

―― ほっとキッチンを開始した経緯やきっかけ、想いについて教えてください。
小林さん:2015年頃、たまたまテレビで子ども食堂の特集を見かけたんです。
それを見て、「このくらいなら自分にもできるかもしれない!」と思ったのが、活動を始めるきっかけでした。
ですが、立ち上げは想像以上に大変で。時には、お叱りを受けることもありましたね。そういった経緯で、当初2015年12月を予定していた開催は延期し、翌月2016年1月8日にようやく初回を開催しました。
立ち上げ当初は小学校低学年の子ども達の参加が中心でしたが、ある時中学校の先生が母子家庭の生徒を連れてきてくれたんです。
「家庭訪問に行ったら、冷蔵庫に何も入っていなかった。少し心配で…」という理由でした。結局その子は2回くらい参加した後、来なくなってしまってしまいました。
多分、周りが小さい子ばかりで居心地が悪かったんでしょうね。
そういった出来事もあり、対象を中高生に見直しました。ただ、「高校を中退している子もいるよね。“中高生”と限定してしまうと、そういった子は来にくくなってしまいませんか?」という意見もあり、『中高生・若者ほっとキッチン・無料学習塾』という現在の活動が始まりました。
―― 10代を対象にした団体は、県内では比較的少ないのではないかと思います。難しい年ごろで、こういった場所に来ることを避けられてしまう気がするのですが、参加者はどのように募集をしているのですか?
小林さん:ここに来ている子たちは、基本的に自分から来たわけではないんです。
紹介を通じてほっとキッチンに来た、連れてこられたというパターンが多いですね。
みんなそれぞれ、何かしら事情を抱えています。表情だったり行動だったり、ここに通ううちに少しずつ変化が現れてくるんです。
家でも学校でもないこの場所で、色々な大人と接することで、子どもたちは自分の中で何かに気づき、少しずつ変わっていく。
周りの大人が、ほんの少し背中を押してあげるだけで、子どもって本当に変わるんですよね。そんな姿を見ると、私たちも思わず感動してしまいます。「ああ、この子、大人になったなあ」って。まるで、おばあちゃんと孫のような関係ですよね。
―― 活動を通じて、利用者の方からの声はありますか?
小林さん:先日、食料配布を利用されている方から、「ほっとキッチンの食材配布のお陰で、1年間何とか生きて来られました」と涙を浮かべて感謝のお言葉をいただきました。驚きましたが、その言葉に私たちの方が勇気をいただきました。
中山さん:配布しているお野菜はスーパーに並んでいるような綺麗なものではありません。
だからこそ、「こんなものを渡して、かえって迷惑なのではないか」と、ずっと申し訳なく思っていたんです。でも、実際に喜んでいただけていることを知って、「このままでもいいんだな。お互いにとって良いことだったんだな」と感じました。
私たちは“あげる側”という立場ではありますが、この活動を通して、人として育ててもらっていると実感しています。本当にありがたいことです。
小林さん:何人かの利用者の方から、「私たちがこんなにいただいていいのでしょうか」と言われることもあります。
受け取る側にも、どこかに葛藤があるのだと思います。だから私は、いつも「いいんですよ!」とお伝えしています。
「今は大変な時期だから、遠慮せずに受け取ってください。そして、将来お子さんが手を離れたときには、今度はあなたが困っているお母さんを助けてあげてくださいね」と声をかけると、とても安心した表情で、「じゃあ、頑張ります」と言ってくださるんです。
―― 今後の計画や、やってみたいことを教えてください。
小林さん:長野市では、中学校の部活動の地域移行を進めています。ほっとキッチンでは絵画教室も行っているので、受け入れが出来ないか模索しています。
高戸さん:子どもを取り巻く環境は、どんどん多様化しています。学校のあり方もこれから大きく変わっていくでしょう。
そうした変化に対して、すべての家庭が十分に対応できるかというと、やはり難しい部分もありますよね。だからこそ、地域がその不足を補い、子どもたちを支えていくのは当然のことだと私たちは考えています。
「子どもは社会の宝」——これは、ほっとキッチンの考え方です。子どもたちにみんなで目を向け、みんなで育てていく。そんな社会になってほしいと願っています。
まとめ
ほっとキッチンを初めて訪れた私も、なぜか懐かしさと安心感を覚える空間でした。
特に印象的だったのは、ボランティアの皆さんの姿勢と熱意です。子どもを取り巻く社会環境に常にアンテナを張りつつ、一人ひとりの事情や性格に寄り添ったサポートの重要性を深く理解されていることが伝わってきました。
社会の状況が目まぐるしく変化する現代において、子どもたちもその変化に対応していかなければなりません。
しかし、それを子ども自身の力だけで乗り越えるのは難しいことです。家庭でも学校でも十分なサポートが得られないとき、子どもたちはどうすればよいのでしょうか。
子ども食堂には、そうした子どもたちを孤立や孤独から守る“セーフティーネット”としての役割も期待されています。
そのため、全国的に子ども食堂の設置や支援の取り組みが広がっているのです。
とはいえ、子ども食堂がただ存在するだけでは十分とは言えません。子どもたちに本当に寄り添うには、正しい知識と丁寧な対応が求められる、非常に繊細で責任のある活動なのです。ほっとキッチンの訪問を通じて、子ども食堂という活動を行う上で大切にすべき考え方を勉強させていただきました。
ここで過ごした時間が、子どもたちの人生を少しでも明るく照らすものであることを、心から願っています。