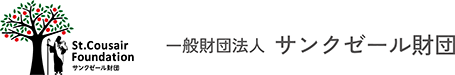日本国内におけるセーブ・ザ・チルドレンの取組み(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)
こんにちは、サンクゼール財団です。
私たちサンクゼール財団は、事業活動を通じて「愛と喜びのある暮らし」の実現に寄与することを目的としています。
中でも、子どもや生活困窮者等への支援は特に注力していきたい分野のひとつです。
一方で、現代の子どもを取り巻く社会課題には、どのような問題があるのでしょうか。子どもを守るためには、どのような配慮が必要なのでしょうか。基礎知識を持ったうえで、尊厳を守る支援活動が重要であると感じています。
そこで当財団は、「子ども」にスポットを当て支援活動に取り組む、公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン様(以下、セーブ・ザ・チルドレン)をお招きし、勉強会を開催いたしました。
日本国内におけるセーブ・ザ・チルドレンの支援活動についてご紹介いたします。
「セーブ・ザ・チルドレン」について
セーブ・ザ・チルドレンの創設は1919年。第一次世界大戦で荒廃したヨーロッパにおいて、イギリス人女性のエグランタイン・ジェブが、敵味方の枠を超えて子ども達への支援に取り組んだことをきっかけに、創設された国際NGO(非政府組織)です。
“生きる・育つ・守られる・参加する「子どもの権利」を、すべての子どもが享受できる世界の実現”というビジョンを掲げ、日本を含む約120の国と地域で子ども支援活動を展開しています。 日本における活動は1986年から開始されました。
“子どもの権利”とは?
セーブ・ザ・チルドレンの活動を紹介する上で、欠かせないキーワードが”子どもの権利”。
この子どもの権利について、包括的にまとめたものが「子どもの権利条約」です。 セーブ・ザ・チルドレンの活動は子どもの権利を土台としています。
権利の主体者である子どもが、権利を行使できるように支援し、子どもの権利が社会全体で保障される社会を実現するために、政策提言や社会に向けた啓発といった活動に取り組んでいるのです。
参考:子どもの権利条約
子どもの権利条約とは、子どもは守られるだけの存在ではなく、権利を持つ主体であることを国際的に保障するとした条約です。誰であっても、どこに生まれ育っていても健やかに、自分らしく育つために必要な「当たり前のこと」を保障しています。
中でも次の4つの一般原則が、子どもの権利条約の土台となる特に重要な権利です。
- 生きる・育つ権利(6条)
- 人種・性・国籍・障害などを理由に差別されない権利(2条)
- 子どもにとって最もよいことを考えてもらう権利(3条)
- 意見を聴かれ、正当に尊重される権利(12条)
子どもの権利条約(日本語訳)
https://www.savechildren.or.jp/about_sc/kodomono_kenri/minkan.html
日本国内におけるセーブ・ザ・チルドレンの活動
日本国内における事業としては、特に次の3分野において活動をしています。
①子どもの貧困
子どもが生活や成長に必要なものやサービス、機会を得られ、可能性を発揮できるよう、直接支援や政策提言に取り組む
②地域NPO支援
地域の非営利団体(NPO)を主な対象とする助成プログラムの実施によって、日常生活における子どもの権利の保障を目指す
③緊急・防災
自然災害や紛争などの影響を受けた子ども・大人が日常を取り戻したり、生活を再建したりできるようサポートしたり、防災に子どもの声が反映され、災害時に子ども達が主体的に行動できるよう、子どもを中心とする防災を推進する
このうち、①子どもの貧困と③緊急・防災に関する取り組みについて、詳しくご紹介いただきました。
日本の子どもの貧困の現状
「2022年国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)によると、日本に住む子どもの相対的貧困率は11.5%。約8~9人に1人の子どもが相対的貧困状態。
さらに、ひとり親世帯における相対的貧困率は44.5%にのぼり、およそ2世帯に1世帯が困窮状態。所得が100万円未満の層が増加している傾向もあります。
参考:相対的貧困とは
相対的貧困とは、”その社会における一般的な生活水準よりも低い状態にあること”を指します。
基準は「等価可処分所得(世帯の手取り÷世帯人数の平方根)の中央値の半分」以下の収入しかない状態を指し、国や地域社会によって水準が異なります。
対して絶対的貧困は国や地域の水準に関係なく、人間としての最低限の生活が満たされない状況を指します。
こういった厳しい経済状況は子どもに対して、様々な影響を及ぼすことが分かっています。
衣食住に関わる経済的困難はもちろん、学習や進学の制限、様々なライフチャンスへの制約など、「その社会で通常経験できることができない」という困難にもつながるのです。
セーブ・ザ・チルドレンが支援者を対象に行ったアンケートでも、「経済的に厳しく、部活を続けられません」(保護者)、「自分たちが進みたい進路を経済的に諦めることのない平等な選択がほしいです。そのことで親を責めたりしたくないからです」(子ども)といった声がありました。
親にとっても子どもにとっても、前向きに生きる気持ちや自己肯定感の低下、社会的な孤立につながる非常に深刻な課題なのです。
支援活動の具体例
①食料品配送事業:「子どもの食 応援ボックス」
給食の提供が無い夏休みや冬休み期間に合わせて、年2回食料品や文具等を詰め合わせた段ボールを配送する事業です。
きっかけは、新型コロナウイルス感染症の拡大下において、生活困窮世帯に対して行ったアンケート。
ある子どもからの「はらへった」という回答を受け、「応援ボックス」事業がスタートしました。
2023年までに約27,000世帯に食品や日用品を届けており、主食の米の他、季節感を感じられる食品や、シャープペンシルや消しゴム等の文具、保護者がほっと一息つける嗜好品等も詰め合わせて届けています。
②高校生への支援:「子ども給付金~高校生活まなびサポート~」
公的支援が薄い高校生を対象に、毎月2万円を給付する事業。対象地域は宮城県石巻市に限定して行われています。
給付金の使い道は「子どもの高校生活に関わるもの」とし、細かい指定はありません。
部活動や教材、修学旅行費などに使用されており、子ども給付金事業を通じて「学びたい、〇〇をしたい、という思いが行動へつながっている」、「毎月2万円が届く安心感、金銭的ストレスが軽減された」という利用者の変化が生まれています。
国内災害時の緊急支援
セーブ・ザ・チルドレンは、東日本大震災の緊急支援から復興まで、長期にわたる支援活動に取り組んできました。
この支援活動を通じて得た知見を活かし、子どもや保護者に特化した支援を行っています。
2024年の能登半島地震の際には、発災直後から避難所で「緊急子ども用キット」として、衛生用品と室内で遊べるおもちゃのセットを配布。
そのほか、自分の思うままに過ごすことができる「こどもひろば」の開催、給食の補食支援を行うなど、子どもにフォーカスした支援活動を実施しました。
災害などの緊急時において、対応が後回しになりがちな子ども達の声や気持ちに寄り添った活動に取り組んでいます。
まとめ
困難な状況にある子どもたちのために、多岐にわたる支援を行うセーブ・ザ・チルドレンの活動をご紹介しました。
彼らの活動は、子どもたちが健やかに成長し、自分らしく生きるための環境を整えることを目指しています。
特に貧困や災害といった状況に置かれた子どもたちが、環境に左右されることなく将来への希望を持ち続けるための支援や配慮は、大変貴重な学びでした。
私たちサンクゼール財団も、今回の学びを基に子どもたちの未来を支えるための支援活動を行っていきたいと考えています。
現場の声に耳を傾け、彼らのニーズに応じた支援を提供することで、より良い社会を築いていくことができると信じ、引き続き活動してまいります。