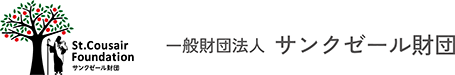第1回助成事業 助成事業採択団体へのインタビュー。活動に対する想いをお聞きしました。(社会福祉法人 長野県社会福祉協議会 前編)
こんにちは、サンクゼール財団です。
当財団は「すべての人に、愛と喜びのある食卓を。すべての人に、温かい光を。」という想いのもと、設立後初となる助成事業を実施いたしました。
今回は、助成団体のひとつである社会福祉法人 長野県社会福祉協議会(以下、県社協)を訪問。
県社協は”中間支援団体”として、子ども食堂の支援現場を支えるともに、独自の”食”を通した支援活動に取り組まれています。
その活動について、まちづくりボランティアセンターの所長・長峰さんと専門員・豊田さんにお話を伺いました。
社会福祉法人 長野県社会福祉協議会 概要

【主な活動地域】長野県全域
【事業内容】“地域福祉の向上”を目的として、生活困窮者や高齢者、障がい者などへの相談支援体制の整備、福祉人材の育成と定着支援、災害時のボランティアセンター運営、地域づくりの推進など、多岐に渡る事業を展開する民間団体。
地域共生社会の実現に向けて、多様な立場の人々が安心して暮らせる「人のあたたかさに包まれる地域社会づくり」を支援している。
【ウェブサイト】https://www.nsyakyo.or.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/egao.pro.nsyakyo/?hl=ja

【お話をお聞きした人】
長峰夏樹さん(写真右):
まちづくりボランティアセンター所長
豊田尊城さん(写真左):
まちづくりボランティアセンター専門員
民間だからこそできる、地域に寄り添う福祉支援
――この度は、当財団の助成事業にご応募いただき、誠にありがとうございました。
私自身もそうでしたが、「社会福祉協議会」とはどのような団体で、どんな活動をしているのか、詳しくは知らない…という方は多いのではないでしょうか。地方公共団体とは異なり、民間団体なのですよね。
長峰さん:そうですね。よく「公務員ですよね?」と聞かれることがありますが、実は違います。
”社会福祉法人”は、いわゆる”団体職員”という枠組みに入る民間団体です。特に私たち(県社協)は、行政からの委託事業や共同事業が多いのもあってか、誤解されることが多いです。
これは社協職員あるあるだと思うのですが、アンケートなどで職種を選ぶ欄に「団体職員」が無いこともあって(笑)。それくらい、少し特殊な立ち位置なのかもしれませんね。
ざっくり言うと、社会福祉協議会は、民間の立場を活かしながら、地域に根ざした福祉活動を展開する団体です。特に私たちが所属する”まちづくりボランティアセンター”では、さまざまな分野に関わりながら事業を進めています。
――「民間の立場を活かした福祉活動」という言葉が印象的です。県社協では、具体的にどのような事業に取り組まれているのでしょうか?
長峰さん:市町村の社協では介護事業の割合が大きいのですが、実は県社協では直接的な介護事業は行っていないのです。
県社協の事務所には、大きく分けて3つの機能があります。
まず、私たちが所属するまちづくりボランティアセンター。こちらでは、サンクゼール財団の助成事業に採択いただいた”広域フードパントリーむすびや”の運営や、困窮者に対する食品の個別配送事業の取りまとめなどを行っています。「困っている人をどうにか助けたい」というボランティア精神を原点に、行政だけでなく、企業や教育機関など多様な団体と連携しながら活動しています。
次に福祉人材センターでは、福祉分野の人材確保や、若者への魅力発信、行政との連携などを通じて、福祉の職場で活躍する人材の育成に取り組んでいます。
最後に相談事業部門は、県内26カ所に窓口が設置されている生活就労支援センター まいさぽを含む、相談事業機能が集約されている場所になります。相談現場の声を真摯に受け止めながら、支援活動に反映させることを心がけています。

所長・長峰さん(写真右)、専門員・豊田さん(写真左)
食品支援の原点と広がり
――令和6年度の助成事業では、生活困窮者への食品個別配送事業と、広域フードパントリーむすびや の運営費を主な用途とする申請をいただきました。まずは、食品個別配送事業について、内容と立ち上げの経緯などを教えてください。
豊田さん:食品の個別配送は、生活就労支援センター まいさぽ などの相談窓口に来られた方を対象とする事業です。
副菜を中心に、家族で7〜10日間程度を賄える程度の食品をお送りしています。初回から4回目までは無料、5回目以降は送料のみいただく形で提供しています。
5回目以降の送料を有料としているのは、一つの歯止めなのです。「食品の支援」のみですと、根本的な自立支援につながるケースはまれです。この食品配送事業の目的は、あくまで相談窓口に来てもらうこと、そして信頼関係を築き、継続的な支援につなげることなので、そのような方針となっています。
長峰さん:この事業のきっかけは、長野県で2015年に生活就労支援センター まいさぽが開設されたことでした。
生活全般の困りごとを相談できる窓口として開設された窓口でしたが、「今日食べるものが何もない」といった、非常に差し迫った状況にある方が相談に来られることもあったのです。相談窓口の現場では「何とかしてあげたいけれど、職員としては何もできない」という悲痛な声が上がっていました。
そんな中、”セカンドハーベスト・ジャパン”という団体が、生活困窮者に対して食品を個別配送しているということを知り、「これなら、直接食品を提供できる。本当に困窮している方に必要な支援ができる!」と思ったのです。
当初は県社協での立ち上げを試みましたが、当時の上司には理解を得られませんでしたね。「貧しいからといって、食べ物を直接配るなんてありえない」とまで言われてしまって。それでも、困っている人がいるという事実は変わりません。
どうにかできないものかと、試行錯誤を重ねました。その結果、長野市社会事業協会さんで社会貢献事業として、個別配送に取り組んでいただくことになりました。配送費も協会側で負担していただき、2015年から県内全域での食品配送がスタートしました。
――上司の理解が得られない中でも奔走されたのですね。現場の切実な声を知っているからこそ、強い使命感を持って行動されたのだと感じます。
長峰さん:そうですね。「困っている人をどうにか助けたい」というのが、私たちの原点です。
コロナ禍に入ると、個別配送のニーズが急激に高まりました。その頃には長野市社会事業協会さん単独での運営から、フードバンク信州さんの協力も得た事業になっていましたが、民間団体同士による独自運営には限界を迎えていました。
同時に、コロナ禍を経て長野県内における”食”の助け合いが活発になりました。「必要とする方々がいるのであれば、活用してほしい」と、食品の寄付を多くいただくようになった一方で、各市町村レベルでは活用しきれない余剰食品が出てきてしまったり、逆に不足する市町村もあったり…そんな課題も生まれてきたのです。
それらの課題を解消するために開設したのが、広域フードパントリーむすびやです。
県社協が取り組む「食品の個別配送事業」は、生活に困難を抱える方々に寄り添い、支援のきっかけをつくる大切な活動でした。
後編では、広域フードパントリーむすびやの取り組みや、団体間の連携によって生まれた新たな支援の広がりについてご紹介します。食を通じて人と人がつながる現場の声を、ぜひご覧ください。
▼長野県社会福祉協議会 ウェブサイト
https://www.nsyakyo.or.jp/
▼長野県社会福祉協議会 Instagram
https://www.instagram.com/egao.pro.nsyakyo/?hl=ja